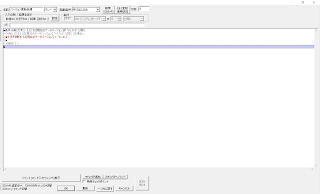次回作向けにスキルを整理していたときの感想などを文字に起こしたら面白いんじゃないかということで、書いてみた記事です。
ひと言ふた言のコメントでも56スキルあると結構な量になるので、とりあえず半分の28スキル+通常攻撃1スキル分を今回は掲載します。
前作レイユウサイでも登場したスキルもケルリートでは多数登場するのですが、基本的なスキルは変えようがないというところでそのままになっています。
とはいえ、アクティブスキルにもスキルレベルの概念が導入されたり、それに合わせて付与呪文の仕様も変わったりしていて、プレイ感はだいぶ違うはず。
ちなみに、共通パッシブスキル(一番左のタブ)は大部分を入れ替えました。入れ替え対象になったパッシブスキルは「ステータス比例強化+成長率アップ」という効果のあるものでした。「成長率アップするなら真っ先に取っちゃおう」という心理が働くし実際自分もそうしていたし、なによりバランス調整が難しいということで、ボツになりました。
スキルツリー制のシステムにおいて「どんな育成方針でもこのスキルはみんな取る」だとか「こんなスキル誰も取らねーよ」という状態は面白くないので……。
ケルリートではそんな状態が完全に解消されたかというと、そんなことはなかったのですが……。ここが次回作への課題で、相当悩みました。
斬る
いわゆる通常攻撃。消費SP0で再詠唱時間は全スキルで最短。
単発威力は低いが回転が速くDPSは悪くないので、パッシブスキル中心に取って攻撃はこれ一本で終盤まで戦うプレイもある。
ちなみに付与呪文でスキルレベルを上げるとしっかり威力が上がる。やってる人がいたかは不明。
前作レイユウサイではダメージ計算式の関係で最強スキルの一角だった。
生命の灯火
残りHPが少ないときに与ダメ・被ダメに補正がかかるパッシブスキル。
HPが減りやすいバランスの関係上活躍できるかと思い実装。
数値設定の問題でv1.0.30になるまでは使いづらいスキルでしたが……。
剣術の鍛錬
物理攻撃の与ダメージ全てに乗算で補正がかかるパッシブスキル。
物理ツリーを取るなら必須なので採用率は高い。
最後の防備
物理攻撃の被ダメージを割合軽減するパッシブスキル。
物理耐性を上げているので、技能+付与呪文の組み合わせ次第では物理攻撃を無効化できる。
魔道の心得
四属性攻撃の与ダメージ全てに乗算で補正がかかるパッシブスキル。
魔法ツリーを取るなら必須なので採用率はやはり高い。物理ツリーにある火属性攻撃「火焔斬り」にも効果は乗る。
緑神の息吹
いわゆる確率食いしばり。
MAX振りして発動率21%。強いか弱いかは人によるかもしれない……。
お守り代わりに振る人はいたかもしれない。
緑神の守護
毎秒HPが回復するようになるパッシブスキル。
ポイントも安いのでとりあえず取っておけくらいの感覚で1振りか5振りする印象。
自然の加護
SPの自然回復量を上げるパッシブスキル。
通常攻撃オンリーで攻めるビルドにしない限りはほぼ採用される。
物質の知識
四属性攻撃の被ダメージを割合軽減するパッシブスキル。
属性耐性を上げているので、付与呪文などを活用すればかなり耐えるようになれる。
通常プレイなら採用率はわりと高い印象。
狩猟の技術
素材ドロップ率を加算で高めるパッシブスキル。
もとからドロップ率は高いので、採用率はあまり高くないかもしれない。
火あぶり
魔法ツリーの基本的な攻撃スキル。火属性。
前方を攻撃できて挙動も素直なので扱いやすいやつ。
魔法ツリーを取るならとりあえず取っちゃうやつ。
氷柱の守り
今作で実装された(同じ技を複数繋げて発動させる)新機能を使うべく実装されたスキル。水属性。
壁のように置き、敵をひっかけて攻撃するのが理想の使い方。
多段ヒットするので、全段当てれば結構強い。
稲妻走り
敵を狙わなくても範囲内なら当たるステキな攻撃スキル。雷属性。
間合いを意識する必要が薄れるので、人によってはこれ中心に据えると思う。
傷ふさぎ
いわゆる回復スキル。
HPに対して大きめのダメージをやり取りするバランスなので、威力は結構強めに設定している。
プレイによっては取らないこともあるが、即時回復で使いやすいこともあり採用率は結構高い。
回復しかしないなら1振りでもいい。MAX振りは付与呪文向け。
魔道の知識
自身の知能(魔法攻撃力)を高めるスキル。
作者は魔法ツリーで育てる時はほぼ確実に取るスキル。
Aキー切替をあまり使わない人は取らないかもしれない。
このスキルが高位の魔法攻撃スキルの前提になっているのは、火あぶり→火焔ばしらのように同属性攻撃スキルを前提にするよりは腐りにくいから。高位スキルは消費も再詠唱時間も重たいので、威力面で一撃をより重くして使ってほしいという思いもある。
こういう前提スキルの決め方は、スキルセット型のアクションRPG特有の感覚かも。
略式術法
詠唱速度を大きく高めるスキル。
デメリットは魔法攻撃力の低下。スキルレベルを上げるとデメリットが軽減されるので、使うならMAX振り推奨。
高位魔法の回転を良くしたい場合は欲しい。
前提が腐るものの物理型で使えばデメリットは踏み倒せる。
大地の怒り
唯一の土属性攻撃スキル。
土属性さんは地味オブ地味で、もともとは実装予定もなかったが、制作途中で1つスキルを追加する必要に迫られて実装した背景がある。
魔法の鎧
再詠唱時間中でもガードが発動するようになるパッシブスキル。
前作レイユウサイでは再詠唱時間中でもガード発動する仕様でしたが、再詠唱時間中はガードできない仕様へ変更したので追加したスキル。
使っている人はあまりいない気がする。ガード、意識すると結構強いのだけど……。
吸魂術法
与ダメの一定割合ぶんHP回復するスキル。
ついでに最大HPも結構強化される。生存特化型にするなら欲しいやつ。
付与呪文にも攻撃ヒット時HP回復するものがあるせいか、採用率は……低い気がしますね……。結構強いんだけども。
火焔ばしら
火属性の高位魔法。消費は重いが威力も重い。特化すれば4桁ダメージがポンポン出るようになる。
単発威力重視ならこれ。最終エリアに刺さるので採用率は高いかもしれない。
魔道の知識で知能を高めてから使いたい。
氷期来訪
水属性の高位魔法。氷柱の守り同様防御を意識したデザインの技。
自身の周囲にダメージ判定が出るので扱いやすいものの最終エリアに刺さらないので難しいところ。
雷鳴招来
稲妻走りの上位版といったところ。確率で連続発動する。
それ以上のコメントがしづらい技ですが、稲妻走りでやってきた人が置き換えることはあったと思う。
言霊反芻
魔法攻撃力アップと次に使う技の消費SP半減という優秀なスキル。
高位魔法を使うなら併用したい。
物理攻撃力バージョンもある。前作レイユウサイでは消費SP半減ではなくSP回復効果がついていて、これを乱発すればSPには困らないという、良くも悪くも便利なスキルだった。
効力分析
弱点突いたときダメージがアップするパッシブスキル。
結構上がるので、魔法ツリーなら欲しい。
物理ツリーでも前提は腐るが効果はしっかり発動するので、相手によっては有効。
効力還元
弱点突いたときSPが回復するパッシブスキル。
効果は優秀なものの、これを取れる頃にはSP自然回復を強化しているはずなので、採用を見送る場合もあると思う。
魔道の衣
HPダメージの一定割合ぶんSP回復するパッシブスキル。
被弾する必要があるので、最大HPを高めていないとしんどい面も……。
取った人、いるだろうか?
元素の盾
確率で四属性攻撃を無効化するパッシブスキル。最大20%。
確率ものなので、取る人は取るし取らない人は取らないでしょう……。
意外と発動するので効果は実感しやすいはず。
四次障壁
四属性攻撃耐性を大きく高めるスキル。
前提スキルと合わせればめちゃつよではあるものの、防御系スキルに枠を割いてもらえるかどうかというと……というところ。
付与呪文にするには強すぎるので難しいところ。
次回は物理ツリーと法陣ツリーです。